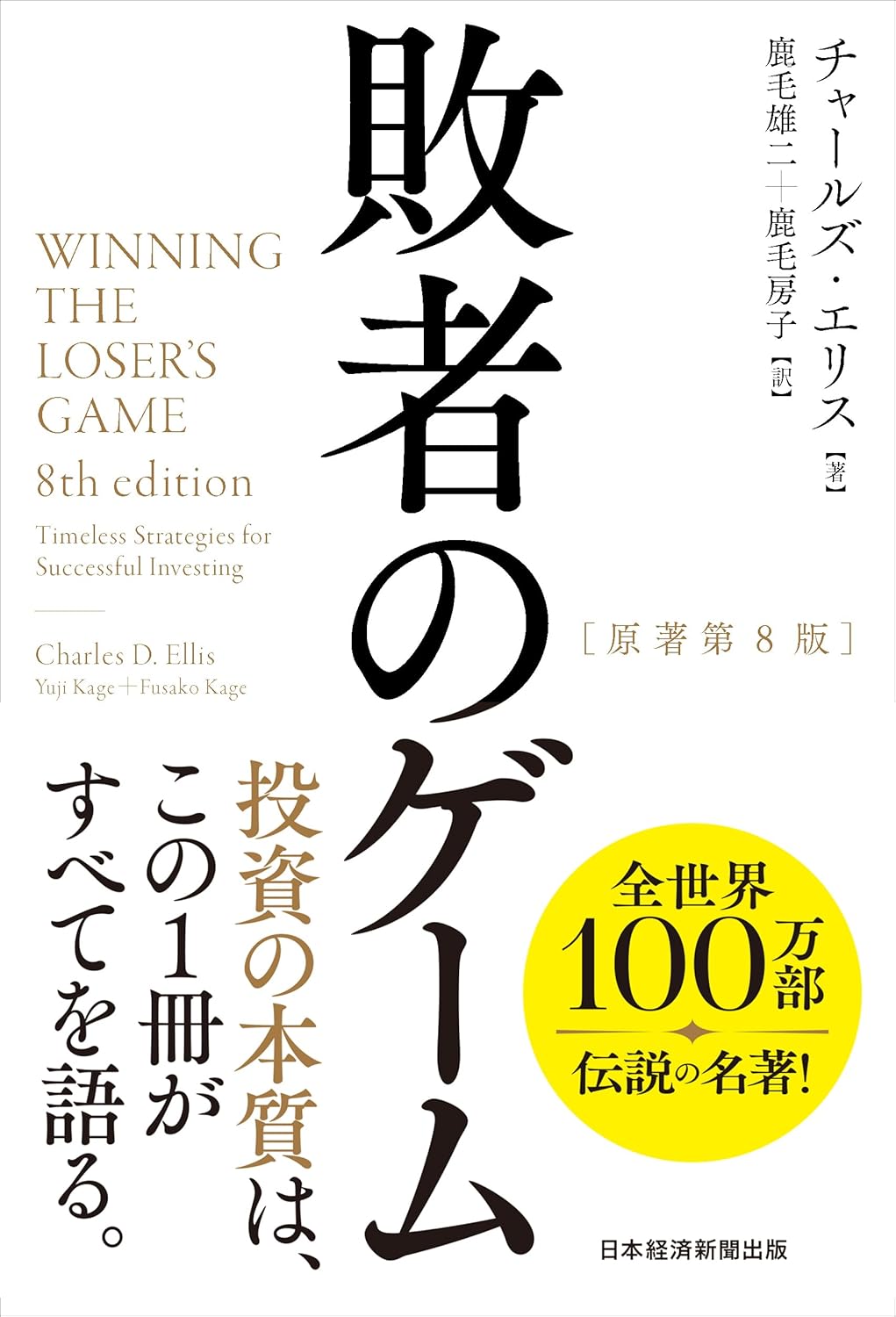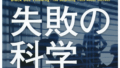「投資」というとどういう方法を思い浮かべるだろうか。「株が安い時に購入して株価が高騰したら売る」このようなイメージを持つ人も多いかもしれない。しかしこれはもはや主流ではない。
まずどうやって安い株の情報や将来高騰する情報をあなただけが手にするのか、これは不可能だ。
近年、個人投資家から絶大な支持を集めているのが「インデックスファンド」である。そのシンプルさと低コストは、従来の投資の常識を覆し、まさに投資の世界に革命をもたらしたと言える。
インデックスファンドとは
インデックスファンドとは、特定のインデックスと全く同じ値動きを目指して運用される投資信託のことだ。「S&P 500インデックスファンド」であれば、S&P 500指数の値動きに可能な限り連動するように設計・運用される。
この運用は「パッシブ運用(受動的運用)」と呼ばれ、市場平均と同じ成果を得ることを目的とする。プロが銘柄を選ぶ手間がないため、運用コスト(信託報酬)が極めて低く抑えられるのが最大の特徴である。
そもそもインデックス(指数)とは何か
インデックス、すなわち「指数」とは、特定の市場や経済全体の動向を把握するために、選ばれた複数の銘柄の価格を基に計算される市場の「体温計」のようなものだ。
市場全体の動きを追うのは不可能だ。市場を代表する銘柄の値動きを一つにまとめて表示し、傾向をシンプルに捉えられるようにしたのがインデックスである。
具体的なインデックスの例を見るとピンと来るはずだ。
| インデックス名 | 対象市場・銘柄 | 特徴 | 作成・管理 |
|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 東京証券取引所プライム市場の全銘柄 | 日本の株式市場全体の動向を測る、時価総額ベースの代表的な指数 | 株式会社JPX総研 (東京証券取引所の親会社) |
| 日経平均株価 | 日本の主要企業225社 | 日本経済新聞社が選んだ225銘柄の平均株価 | 日本経済新聞社 |
| S&P 500 | 米国の大手企業500社 | 米国株式市場の動向を示す代表的な指数 | S&P Dow Jones Indices |
| MSCI ACWI(オール・カントリー・ワールド・インデックス) | 全世界の株式市場の多様な業種 | 各国の株式市場で流動性が高く、時価総額が大きい主要企業が対象 | モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル |
インデックス投資で資産が増える理由:この3つの力があなたのお金を増やす
インデックスファンドに投資したからといって、なぜ資産が増えるのか、その理由がピンとこない人もいるだろう。株価が上がるからか、それともインフレのせいか。
実は、資産が増えるのには主に三つの強力な理由が複合的に作用している。例えば「オルカン」こと全世界株インデックスファンドに投資するメリットは、この三つの恩恵を漏れなく享受できる点にある。
1. 資本主義経済の成長
インデックスファンドで資産が増える最も根本的で強力な理由は、人類全体が営む資本主義経済が、長期的には成長し続けるという前提だ。
オルカンが連動を目指す指数(MSCI ACWIなど)は、日本を含む全世界の企業の集合体を表している。
- 企業の利益拡大: 企業は常に新しい技術や製品、サービスを生み出し、効率化と競争を通じて利益を拡大しようと努めている。この全世界の企業の利益が積み重なることによって、その企業の価値(時価総額=株価)は長期的には上昇していく。
- 最強の「エンジン」に投資: 特定の国や産業に賭けるのではなく、全世界の「成長する企業」というエンジン全体に低コストで参加し続けるのがインデックス投資だ。特定の企業が衰退しても、指数は自動的に成長著しい新しい企業に入れ替わる(新陳代謝)。この仕組みが、世界経済の成長という恩恵を確実に取り込むことを可能にする。
つまり、株価が上がり続けるのは、人類の経済活動が長期的に膨張・成長し続けるからにほかならない。
2. 配当金の自動再投資と複利効果
資産を加速度的に増やす影の主役が、「配当金」の自動的な再投資による複利効果である。
- 配当の発生: オルカンの構成企業は、利益の一部を配当金(インカムゲイン)として株主に還元する。
- 自動再投資の仕組み: オルカンなどの多くのインデックスファンドは、この受け取った配当金を投資家が現金で受け取るのではなく、ファンド内で自動的に再投資する。
- 利益が利益を生む: 再投資された配当金は、次の期間にさらに利益を生み出すための新たな元本となる。この「利益が利益を生み、それがさらに大きな利益を生む」というサイクルこそが複利効果であり、長期投資において資産を爆発的に増やす最大の推進力となるのだ。
仮に株価が停滞しても、配当金が再投資されることで、資産の増加は止まらない。
3. インフレヘッジ(実質的な購買力の維持・増加)
インフレは、資産を増やす「原因」というより、資産の「実質的な価値」を守る役割を果たす。
- 貨幣価値の目減り: インフレとは、モノの値段が上がり、現金の価値が目減りすることだ。ただ現金を持っているだけでは、実質的な購買力は確実に失われていく。
- 株式は実物資産: 株式は企業の所有権であり、企業が持つ工場や製品といった実物資産に裏付けられている。インフレでモノの値段が上がれば、企業の売上や利益も増加しやすい。
- インフレを凌駕: インデックスファンドを通じて資産を運用していれば、企業利益の成長を享受することでインフレ率を上回るリターンが期待できる。これにより、インフレによる貨幣価値の目減り分を補い、さらに資産を実質的に増やせるのだ。
インデックスファンドは、経済成長と複利効果という二つの力で資産を増やしつつ、インフレからあなたの資産の購買力を守る役割も同時に果たしているのだ。
究極の強み:世界の「金儲けトップ企業」に自動投資
インデックスファンドが長期投資の最適解とされる最大の理由は、その構成銘柄の自動的な「新陳代謝」にある。
S&P 500や「オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)」といった指数に組み込まれているのは、その時点で世界で最も金儲けが上手く、時価総額が大きい、最も勢いのあるトップ企業群だ。
これらの指数は銘柄を固定しない。テクノロジーの進化や産業構造の変化により、企業の勢いが衰えたり、新興企業が急成長したりすると、指数は定期的に構成銘柄を入れ替える。
つまり、インデックスファンドに投資するということは、「未来の勝者を自分で予測する手間」をかけずに、常に時代をリードする企業群に、自動的かつ低コストで投資し続けることを意味するのだ。
過去の栄光と影:アクティブファンド・毎月分配型の時代インデックスファンドが台頭する前、投資信託の主役は「アクティブファンド」であった。
アクティブファンドの流行と「高コストの壁」
アクティブファンドは、専門家(ファンドマネージャー)が市場平均を上回るリターンを目指して積極的に銘柄を選定・売買する(アクティブ運用)ファンドだ。高い運用コストを支払ってでもプロの知見に期待が集まっていたが、「長期で市場平均を上回り続けるファンドはごく少数である」という事実が統計的に証明され、その優位性は揺らいでいった。
このコストの差が、長期投資のリターンに致命的な影響を与える。アクティブファンドの信託報酬は、一般的に年率1.0%から2.0%程度と高い水準にある。
コスト負担の具体的試算と視覚化
信託報酬はファンドを保有している限り、毎日、自動的に資産から差し引かれ続けるコストである。仮に投資資産を1,000万円とし、信託報酬を比較してみよう(※税抜きで計算)。
| ファンドの種類 | 信託報酬(年率) | 年間コスト(1,000万円に対して) | 10年間(累積のコスト差) |
| アクティブファンド | 2.0% | 20万円 | 190万円の負担増 |
| オルカン(低コストインデックス) | 0.1% | 1万円 | 合計10万円 |
年間で19万円ものコストの差が生まれ、資産額が1,000万円のまま維持されたとしても、10年間で累積のコスト差は190万円にも達する。
年間20万円というコストは、ファンドの運用成果とは関係なく、資産から日々、確実に差し引かれていく。「市場平均を上回るリターンを年間2%以上稼ぎ続けなければ、インデックスファンドに負ける」という高コストの壁こそが、アクティブファンドの優位性を揺るがした最大の要因だ。
毎月分配型のブームとその罠
日本市場では2000年代以降、「毎月分配型ファンド」が一世を風靡した。毎月安定した分配金を受け取れる仕組みが人気を集めたが、分配金が運用益だけでなく元本を取り崩して支払われるケースも多く、長期的な投資効率が悪いという問題点が指摘され、その人気は沈静化に向かった。
「市場に勝って利益あげ続けるの無理じゃね?」という気づき
インデックスファンドの誕生は、実は、一人の銀行員と一人の学生の偶然の出会いから始まった。
インデックスファンドの誕生に深く関わったのが、当時ウェルズ・ファーゴ銀行に勤務していたジョン・マックーンだ。彼は、シカゴ大学のビジネスマン向けセミナーで、後に投資の基本理論となる『効率的市場仮説』を学んだ。
効率的市場仮説とは、「現在の株価は、将来に対するあらゆる情報をすでに織り込んだ上で形成されているため、世の中にある既知の情報をもとに、投資で恒常的に(継続的に)利益を上げることはできない」という考え方を指す。
この理論は、アクティブファンドの存在意義を根底から揺るがすものだった。つまり、プロの専門家でも市場に勝ち続けるのは不可能であり、ならば市場平均と同じ成果を得る商品こそが、手数料の分だけ投資家にとって有利になる、という画期的なアイデアが生まれたのだ。
こういう気づきを経て1971年にサンフランシスコのウェルズ・ファーゴ銀行が立ち上げた米国株式ファンドがインデックスファンドの元祖なのだ。
だったら個人でS&P500構成銘柄買えばよくね?→無理です
「インデックスという指標があるなら、個人でそれに合わせて個別銘柄を売買すればいいじゃないか」と考える人もいるかもしれないが、それは現実的ではない。S&P500やTOPIXといった株価指数への連動投資を個人が直接行うのは、資金的・物理的に不可能に近い作業である。
指数に連動する投資が現実的ではない主な理由は、以下の3点に集約される。
1. 銘柄数が多すぎ、莫大な資金が必要である
S&P500は、アメリカの主要な約500銘柄の時価総額に応じて構成されている。指数に完全に連動させるためには、これらの500銘柄すべてを、正確な比率で保有しなければならない。
- 資金の制約:最低購入単位で購入するだけでも、すべての構成銘柄を揃えるには非常に大きな資金が必要となる。
- 銘柄の偏り:時価総額加重平均型の指数(S&P500やTOPIXなど)では、一部の巨大企業(例:GAFAM)が指数全体の大きな割合を占めるため、その比率を個人の力で再現するのは困難である。
2. 絶え間ない「リバランス」の手間とコスト
株価は刻々と変動しており、それに伴い各銘柄の時価総額(指数に占める割合)も変化する。指数に完璧に連動した状態を維持するためには、保有比率がずれるたびに、すべての銘柄を売買して比率を調整(リバランス)しなければならない。
- 取引コストの増大:頻繁な売買は、手数料や税金を積み重ねることになり、指数が本来示すリターンを大きく下回る結果を招く。
- 膨大な手間:個人が500銘柄以上の比率を監視し、正確なタイミングで売買指示を出すという作業は、現実的に不可能である。
3. 指数の「銘柄入れ替え」に追随できない
指数は、市場の変化を正確に反映させるため、構成銘柄を定期的に見直し、入れ替えを行う。
- 個人投資家が、指数提供元が行う銘柄の採用や除外といった調整に、迅速かつ完璧に追随することは極めて困難である。もし追随が遅れれば、その時点で指数との連動性は崩れてしまう。
結論として、個人がS&P500などの指数への連動を目指す最も合理的で低コストな方法は、「インデックスファンド」や「ETF」といった金融商品を利用することだ。これらの商品は、プロが自動的にリバランスや銘柄入れ替えを行い、極めて低いコストで指数との連動性を保ってくれる。
また投資信託においては、組み入れられた株式の配当金は自動的に再投資され、また、日本株の株主優待についても、可能な限り現金化されて信託財産に組み込まれ再投資されるのが基本である。
投資思想の古典:名著と専門家の提言
インデックスファンドの思想的な基盤を確立したのは、名著と、その合理性を訴え続けた専門家の存在だ。
ウォール街のランダム・ウォーカーと敗者のゲーム
バートン・マルキールの著書『ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理』は、市場の株価が予測不能なランダムな動きをするという「効率的市場仮説」を解説し、市場全体(インデックス)を買うのが最も合理的であると結論づけている。
また、チャールズ・D・エリスの『敗者のゲーム』は、高コストでミスを犯しやすいアクティブ運用を避け、「市場平均に負けない」ことを目指すインデックス投資こそが最適戦略だと説いている。
証券会社出身のプロ、山崎元氏の提言
経済評論家の山崎元氏(故人)は、証券会社や信託銀行などの金融機関で長年勤務した経験を持つプロでありながら、一貫してインデックス投資を強く推進した人物だ。
彼は、自身が働いていた業界が販売する高コストな毎月分配型投信やファンドラップといった商品を「やってはいけない」「金融機関にだまされないように」と厳しく批判した。その理由も、高すぎる手数料が投資家個人のリターンを確実に食い潰すという、極めて合理的なものに基づいている。
専門知識を持つプロが、自社の都合ではなく、投資家にとって最も合理的な「低コストのインデックス投資」こそが正解だと声を上げ続けたことは、インデックスファンドが一般に普及する上で決定的な影響を与えたと言える。
低コストと自動新陳代謝こそ最強の武器
インデックスファンドは、低コストと市場の成長への自動的な連動という二つの強力な武器で、長期的な資産形成の主流となった。アクティブファンドの高コストの壁を避け、誰でも簡単に、世界のトップ企業の恩恵を享受できる、現代の合理的な投資の形である。