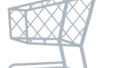ランニングと飲酒。一見すると何の共通点もなさそうに見えるこの二つの行為だが、意外にもいくつかの類似点がある。一方で、身体にもたらす効果や習慣化の質の違いを見ていくと、それらはまるで表と裏、光と影のような対比をなしている。
健康のためにランニングを始めた人が、いつの間にか毎日走らずにはいられなくなるように、気晴らしのつもりで始めた飲酒が、毎日のルーティンに組み込まれてやめられなくなるという現象は、どちらも「快感」や「安心感」に由来する依存の一種とも言える。
毎日やりたくなる中毒性
ランニングにはまると、走らない日が不安になる。身体がうずく、落ち着かない。怠けたら走れなくなるんじゃないか。距離や時間、ペースを記録するアプリに空白ができるのが気になる。多少の雨でもどうせ汗をかくんだからと家を出てしまう。出張先や旅行先にもウェアとシューズを持っていきどこかで時間を作って走りたくなる。「今日は走れなかったな」と思うだけで、まるで自分の一日が不完全であったかのように感じることもある。
飲酒も、似たような傾向を持つ。最初は週末だけ、仕事終わりの金曜だけにしていたはずが、気づけば月曜にも缶ビールのプルトップを開けている。「今日は疲れたから一杯だけ」「明日は早いけど軽く飲むだけ」と理由をつけて、飲酒の頻度が増えていく。やがて飲むのを我慢できなくなる。飲まないというのが不自然に感じるようになる。これは完全に依存に陥っている。
どちらも、心のどこかに「それをしないと不安」という感覚が芽生える。ランニングは健康的な依存と言われることもあるが、その根底には「何かをやらないと落ち着かない」という心理が働いており、構造としては驚くほど飲酒と似ている。
ハイになるという報酬
ランニングには「ランナーズ・ハイ」と呼ばれる状態がある。これは、走っている最中、または走り終えたあとに、気分が高揚し、幸福感が増す現象である。エンドルフィンやドーパミンといった神経伝達物質の分泌によって生じるこの状態は、数時間にわたって持続することもあり、「走るとスッキリする」「嫌なことを忘れられる」と感じる要因になっている。
一方、飲酒にも即効性のある“ハイ”がある。アルコールを摂取すると数分で脳に作用し、理性をやわらげ、気分を高揚させる。笑いや会話が弾み、人によっては大胆になり、普段できないようなことに手を出すこともある。だがそのハイは、あくまで一時的なものであり、必ず下降局面がやってくる。
つまり、どちらも「ハイ」になるが、ランニングはじわじわと上がり、その余韻が長く続く。飲酒は急激に気分が上がるが、同じく急激に下がり始める。そして最終的には「眠気」や「だるさ」「自己嫌悪」へと繋がることすらある。
一人でできる、という共通点
ランニングも飲酒も、一人で完結できる。気軽に始められ、誰にも迷惑をかけずにできるという点で非常に似ている。ひとりランニングは、自分と向き合う時間であり、思考を整理する時間でもある。誰かと走るのも良いが、自由気ままに走る時間には、何ものにも代えがたい魅力がある。
飲酒も同様である。誰かとワイワイ飲むのも楽しいが、ひとり好きなツマミで宅飲みをするのが好きな人も多いだろう。テレビを見ながら、音楽を聴きながら、考え事をしながら酒を飲む。ひとりの時間をじっくり味わう手段として、酒は強力なツールとなる。
だが、「一人でできる」という気軽さが、それを制御できない状態へとつながってしまう点は要注意である。誰にも咎められないからこそ、歯止めが効かなくなるのである。
経済的負担の違い
似たような性質を持つ二つの行為だが、経済的な負担には大きな差がある。ランニングに必要なのは基本的にシューズとウェア、そして多少の交通費くらいだ。マラソン大会に出場すれば、参加費や宿泊費がかかることもあるが、それでも出費としてはさほど重くない。
一方、飲酒には常にお金がかかる。酒代、つまみ代、居酒屋の飲食費、さらにはキャバクラやスナックに通い始めれば、その支出は加速度的に膨らんでいく。「ちょっと一杯」の積み重ねが、月末には「え、こんなに使ってたのか?」という事態を引き起こす。
日々の支出という面でも、長期的な健康被害による医療費という面でも、飲酒のコストは見えにくいところで大きくのしかかってくる。
ワタシは酒に金をかけないが、ランシューズにも金をかけたくない。アシックスのJOLTシリーズは安くて高品質だ。フルマラソンにもこのシューズで出た。
身体への影響:引き締め vs だらしなさ
ランニングを続けると、自然と身体が引き締まってくる。脂肪は落ち、筋肉はつき、心肺機能が向上する。見た目が変わるだけでなく、階段を上るときの息切れや、日常の疲れにくさなど、さまざまな面でプラスの変化が感じられる。
飲酒はその逆である。腹が出てくる、顔がむくむ、皮膚の張りが失われる。アルコールは筋肉の分解を促進するうえ、深い睡眠を妨げるため、回復力も落ちる。飲みながら食べるつまみも脂っこく、塩分が高いものが多く、健康的とは言い難い。
一言でいえば、ランニングは身体を美しく変えてくれるが、飲酒は身体をだらしなくしてしまう傾向がある。
翌日に響くかどうか
ランニングは、たとえ夜に走っても、翌日のパフォーマンスを下げることはない。むしろ、軽い疲労感の中に、心地よい充実感が残り、寝付きがよくなり朝の目覚めがよくなることさえある。
飲酒は違う。どんなに適量を守っても、眠りが浅くなる。特に深酒した翌朝は、倦怠感、胃のムカムカ、頭痛など、完全に「罰ゲーム」のような状態に陥る。二日酔いという副作用の存在は、飲酒にとって最大のデメリットである。
また、早朝に走ろうと思えば、前日の夜の行動が重要になる。夜ふかしして飲酒すれば、当然、早起きして走ることは難しい。習慣としてランニングを取り入れたいなら、飲酒とどう折り合いをつけるかが非常に大切なポイントになる。
どちらを選ぶか
結局のところ、ランニングと飲酒は、「快楽」と「報酬」という同じ回路を別方向に使っている行為である。どちらも気分転換になり、気持ちを高めてくれる。しかし、その「先」にあるものが決定的に異なる。
ランニングの先にあるのは、健康、充実感、成長、そして自信である。飲酒の先にあるのは、怠惰、後悔、浪費、そして疲労である。
もちろん、酒を完全に否定する必要はない。ほどほどにたしなみ、付き合い方を工夫すれば、酒もまた人生の潤滑油になり得る。ただし、それが主役になってはいけない。主役はあくまで「自分自身」であり、「自分の未来」であるべきだ。
ランニングは、その未来を作る力を持っている。今日も走るかどうかは、明日の自分をどうしたいか、という選択に他ならない。