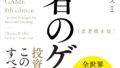税や社会保険制度を聞きかじってファイナンシャルプランナー面をする人を見たことがないだろうか。何を隠そう私はそんなエセファイナンシャルプランナーの一人だ。
そんなエセファイナンシャルプランナーが口をそろえて言うことの一つが「確定拠出年金は美味しい」である。
「美味しいっていうけど、手取りが減るし要するに貯金でしょ、だったら自分で貯めたらいいんじゃないの」
選択制DCを検討しているビジネスパーソンの多くが抱えるこの疑問に、年収700万円、扶養家族ありのケースで具体的な試算結果を交えながら考えてみたい。
DCの最大のメリットである「節税効果」と、唯一ともいえるデメリット「将来の社会保険給付の減少」のどちらが上回るのか。リアルな数字で検証する。
企業型DCの拠出タイプ
会社員が利用できる企業型DCには、会社と社員の「お金の出し方」でいくつかのパターンがある。今回取り上げる選択制タイプ(給料の一部を年金掛金にするか選ぶ)のほかに、メインで使われているのは次の2つだ。
1.会社拠出型
会社拠出型はシンプルに、会社(企業)が掛金全額を拠出するパターンだ。
- 誰がお金を出す? 会社のみ
- ざっくり言うと? 会社が福利厚生として「全額」負担してくれるから、従業員は自分の給料からお金を出す必要がない。もらえるものはもらえばいい。悩む必要はない。
2. マッチング拠出
マッチング拠出は、会社の掛金に社員が自分の給料からお金を上乗せするパターンだ。
- 誰がお金を出す? 会社と従業員
- ざっくり言うと? 会社が一定額を出してくれた上で、さらに「自分で積み立てたい」という人が、会社の拠出額の範囲内で上乗せできる仕組みだ。自分の拠出分は全額所得控除になる。
- のちに述べる選択型DCの「掛け金全額非課税」「社会保険料算定外」とは少し異なる。
3.選択型DC
今回シミュレーションするのは、会社員が給与の一部をDCの掛金として拠出する「選択制確定拠出年金(選択制DC)」だ。
選択制DCの仕組みを再確認する。
- 選択しない場合:その分が通常の給与として支払われる。
- 選択した場合:その分がDCの掛金として口座に積み立てられる。
DCの掛け金とした場合は給与の手取りは減ることになる。Gクラスのローンが組めなくなる。悲しい。しかし悲しむのはまだ早い。
選択制DCの基本:「給与で受け取るか、DCに回すか」の選択
会社員が給与の一部をDCの掛金として拠出する「選択制確定拠出年金(選択制DC)」のシミュレーションをしてみたい。
DCの掛金は、税法上「給与」として扱われないため、所得税・住民税だけでなく、社会保険料の計算対象からも外れる。これが「美味しい」と言われる所以である。
今回は、DCの月額拠出上限額に近い月額55,000円(年間660,000円)を拠出するケースで試算した。
【シミュレーション前提】
- 年収総額(DC掛金含む):700万円
- 扶養家族:妻(専業主婦)、子供1人
- DC拠出額:月額55,000円(年額660,000円)
55,000円をDCに回すか、給与で受け取るか?
結論から言うと、この55,000円を「給与として受け取った場合」と「DCに拠出した場合」では、あなたの手元に残る資産に大きな差が生まれる。
給与として受け取った場合の「目減り」に焦点を当てて比較しよう。
| 項目 | パターンA:5.5万円を給与として受け取る | パターンB:5.5万円をDCに拠出する |
| 貯金・積立の元となる金額(年間) | 660,000円 | 660,000円 |
| 差し引かれる税金・社会保険料(年間) | 約192,000円 | 0円 |
| 手元に残る金額(貯金・積立可能額) | 約468,000円 | 660,000円 |
| 目減り・損失額(年間) | 約192,000円 | 0円 |
| 目減りの割合 | 約29.1% | 0% |
| 将来の運用益 | 課税対象(約20%の税金) | 非課税 |
驚くべき事実:年間約19万円の「目減り」
もしあなたが「DCには回さず、給与で受け取って自分で貯金しよう」と考えた場合、貯金に回せる金額は66万円ではなく、税金と社会保険料で約19.2万円が引かれた約46.8万円になる。
つまり、DCに拠出しないことで、約29%もの金額が貯金前に消えてしまうのだ。あなたは66万円を受け取るつもりだったのに、その66万円はあなたの手元に届く前に「所得税徴税」「社会保険料徴収」を食らって46.8万円にまで目減りしてしまった。道草を食ってしまった。
DCに拠出すれば、この約19.2万円は一切引かれず、そのまま全額(66万円)が非課税の状態で老後資産として積み立てられる。これがDCの最大にして最強のメリットである「拠出時の非課税効果」だ。
退職所得控除のメリット
企業型DC(企業型確定拠出年金)やiDeCo(個人型確定拠出年金)の資産を一時金として受け取る場合、税制上の「退職所得」として扱われ、他の所得に比べて極めて優遇される。これもDCの大きな節税メリットだ。
「退職所得が税制上でメリット?は?」という状態かもしれない。簡単に解説する。
1. 退職所得税制の二大優遇措置
退職所得は、長期の積み立て(勤労)を優遇するため、以下の強力な非課税・軽減措置が適用される。
① 退職所得控除(非課税枠)の適用
DCの加入期間(勤続年数)に応じた「退職所得控除」が適用され、一時金から控除額が差し引かれ、その分は非課税となる。控除額は勤続年数が長くなるほど大きくなる。
| 勤続年数(DC加入期間) | 控除額の計算式 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
例えば、加入期間が30年の場合、1,500万円までが非課税となる。この巨大な非課税枠により、多くの加入者はDCの全額を非課税で受け取ることが可能である。
② 課税対象額のさらなる半減(1/2課税)
退職所得控除を差し引いて残った金額(課税対象額)は、課税対象をさらに半分にしてくれる。
課税退職所得金額 =(一時金の額 – 退職所得控除額) ×1/2
これにより、課税される所得そのものが大幅に圧縮され、適用される税率も低くなるため、税負担が最小限に抑えられる。
2. 要点と注意点
要点
DCは「掛金拠出時」「運用益発生時」「一時金受取時」の3つのフェーズで税制優遇(トリプルメリット)があるが、この退職所得控除は、最終的な手取り額を最大化する上で最も重要なメリットである。
注意点
企業からの通常の退職金とDCの一時金を同じ年に受け取る場合、退職所得控除の枠は両方の合計額に適用される。控除枠が重複し、税負担が増える可能性があるため、受け取り時期の分散など、事前にシミュレーションと検討が必要である点は覚えておいてほしい。
退職金のしょぼい企業に勤めているなら気にしなくていい。
DC vs. 特定口座 20%の税金がない世界
分配金を出さない投資信託(無分配型)で運用する場合、特定口座でも利益確定(売却)するまで課税は繰り延べられるため、「運用期間中の複利効果」という点では、DCと特定口座に実質的な違いはないように見える。
しかし、DCの「運用益非課税」は、出口(売却時)の税金を丸ごとゼロにすることで、最終的なリターンに決定的な差を生み出す。
1. 運用期間中の複利効果は「同等」
分配金を出さない投資信託を特定口座で運用する場合、以下のようになる。
- 利益の発生: 基準価額が上昇するにつれ、含み益が増える。
- 課税の繰り延べ: 含み益は売却するまで課税されない。
- 複利効果: 課税されていない含み益(利益の100%)が次の値上がりの元本となるため、運用期間中の複利効果はDCと変わらない。
2. 最終的なリターンに生じる決定的な差
DCの「運用益非課税」の真の破壊力は、この複利で増やした利益を、そのまま全額手元に残せる点にある。
| 項目 | DC(確定拠出年金) | 特定口座 | 差額(税金) |
| 投資元本 | 100万円 | 100万円 | — |
| 運用益 | +200万円 | +200万円 | — |
| 売却益合計 | 300万円 | 300万円 | — |
| 譲渡所得税 (約20%) | 0円(非課税) | 200万円×20.315%≒40.6万円 | 40.6万円 |
| 最終的な手取り額 | 300万円 | 約259.4万円 | 40.6万円の損失 |
DCの優位性
- 出口課税の排除: 複利効果で雪だるま式に増やした利益の全額(200万円)に対して、売却時に税金が一切かからない。
- 非課税枠の適用: さらに、受け取り時には「退職所得控除」という巨額の非課税枠が適用されるため、実質的に運用益の非課税に加え、元本も含めた税制優遇を受ける。
特定口座の場合、売却時に運用益の約20%が徴収される。これは、あなたが長年かけて積み上げてきた複利の成果を、最後の最後で国に徴収されることを意味する。
DCは「非課税の雪だるま」を最後まで守る
分配金がない無分配型の商品で運用する場合、DCと特定口座の複利効果は運用期間中こそ変わらない。しかし、DCは「売却時の税金という最後の壁」を完全に排除することで、非課税の複利効果を最終的な手取り額として確定させる。
これが、長期積立商品において、DCが特定口座や他の課税口座を凌駕する最大の優位性だ。
DCのデメリット:将来の社会保険給付への影響と資金ロック
選択制DCの掛金が社会保険料の算定基礎(標準報酬月額)から外れることで、社会保険料は安くなる。しかし、標準報酬月額が下がることで、将来受け取る社会保険給付もわずかに減少する。また60歳まで解約はできない。
これがDCのデメリットであり、不安に感じる人も多い点であるため、具体的に考察した。
1. 老齢厚生年金の減少額
DC拠出によって年間の標準報酬月額が下がった場合、将来受け取る老齢厚生年金はどれだけ減るのだろうか。
- 前提: 標準報酬月額の差額5万円が40年間続いたと仮定
- 結果: 年間での年金減少額は約3,288円
年間約19.2万円の節約効果と比較すると、老齢厚生年金の減少額は極めて小さい。生涯で受け取る年金の総額を考慮しても、DC拠出による経済的メリットが大きく上回ると言って間違いない。
2. 休業時の給付(傷病手当金・出産手当金)の減少
傷病手当金や出産手当金は、「標準報酬月額の平均」を基に計算される。標準報酬月額が下がると、これらの給付金も減少する。
- 標準報酬月額の差: 58万円 →53万円に減少
- 傷病手当金の日額減少額: 約1,111円
もし、病気や出産で6ヶ月間休業した場合、手当金の総額で約20万円の減少につながる可能性がある。
このデメリットは、「万が一」のリスクに備える給付が減るという点だ。DC拠出の確実な節約効果と、休業時の給付減少という「リスク」を天秤にかける必要がある。
3.原則「60歳まで資金ロック」
DCは老後のための年金制度だ。積み立てた資産は、原則として60歳になるまで引き出すことができない。
- 途中の現金化不可 「ローンの繰り上げ返済に使いたい」「突然メルセデスGクラスに乗りたくなった」と思っても、途中で解約したり、現金化して引き出したりすることは不可能だ。
- ポイント 流動性(いつでも使えること)を犠牲にして、税制優遇を受けながら老後資金を確保する仕組みである。老後資金でGクラスに乗るんじゃない、シエンタにしとけということだ
なお「住宅ローンの繰り上げ返済」はやる必要はないし、やるべきじゃないとワタシは考えている。理由は別のエントリーで述べたい。
4.死亡時の扱いは「税制優遇付きの特殊な相続」
加入者が亡くなった場合、それまで加入者が積み上げ運用されたDCの資産は「死亡一時金」として遺族に支払われる。これは必ずしもデメリットではない。むしろ、税制面で有利になる可能性がある、特殊なルールだ。
- 非課税枠あり この一時金は「みなし相続財産」として扱われるため、「法定相続人1人あたり500万円」の非課税枠が適用される。
- 注意点 通常の預貯金とは異なり、受取人が遺族の固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外になることが多い。誰が受け取るか(受取人の指定)や、相続税の申告手続き(非課税枠の計算)が通常の財産と異なるため、特殊な手続きが必要になることには注意が必要だ。
拠出の判断は「メリット」と「リスク」のバランス
今回の試算結果から、選択制DCに上限額の月5.5万円を拠出することの判断は、以下のようになる。
| 項目 | メリット(確実な経済効果) | デメリット(将来・リスク時の影響) |
| 毎年 | 約19.2万円の税金・社会保険料が確実に節約できる。 | ほとんど影響なし(年金減少は微小) |
| 生涯 | 非課税で運用でき、受取時も優遇される。 | 老齢厚生年金は年約3,300円の減少。 |
| リスク時 | ― | 長期休業時の傷病手当金・出産手当金が数十万円単位で減少する可能性がある。 |
結論
「確実に資産形成を進めたい」のであれば、DCの節税効果(年間約19.2万円)は圧倒的なメリットであり、上限額の拠出を強く推奨する。全ツッパしてほしい。
自分のライフプランとリスク許容度に応じて、DCという国の強力な支援策を最大限に活用してほしい。Gクラスに乗りたいという気持ちはわかる、ワタシもGクラスに乗りたいが我慢している人間の一人だ。レゴのGクラスでも組み立てながら冷静になってほしい。
オマケ:税金と社会保険料の「ブラックボックス」
確定拠出年金(DC)のメリットを語った後だが、「そもそも、なんで給料から税金や社会保険料が引かれるんや?」というピュアなあなたの疑問に答えておこう。
年収700万円と聞くと、単純計算で12で割れば月々約58万円が手取りになると思いがちだが、実際はそうはいかない。会社員の場合、年収から問答無用で「公的な費用」が差し引かれている。
ここでは、DCに加入しない場合の年収700万円のモデル家庭(妻専業主婦、子供小学生)で、年間でどれだけの費用が引かれているのか、その内訳を「おまけの超入門編」として解説する。
ステップ1:まず引かれる「社会保険料」
あなたの給料から最初に引かれるのが「社会保険料」だ。これは「税金」とは別物で、病気や老後、失業など、万が一のときに国が助けてくれるための積立金のようなものだと思ってほしい。正確には積み立てているわけではないのだが。
社会保険料は、「給与の額」に応じて機械的に計算され、会社とあなたが折半(半分ずつ負担)している。
社会保険料の内訳と年収700万円の場合
あなたの給与明細で特に金額が大きいのは以下の3つだ。
| 項目 | 目的 | 年間保険料(概算) |
| 厚生年金保険料 | 老後の年金、障害を負った時の保障など | 約64万円 |
| 健康保険料 | 病院での医療費が3割負担で済むための費用 | 約35万円 |
| 雇用保険料 | 失業したときの手当(失業保険)のための費用 | 約1万円 |
| 合計 | 約100万円 |
このモデルケースでは、年収700万円からまず約100万円が社会保険料として引かれてしまう。これは、税金と違い「控除(非課税)」という考え方はほとんど適用されないため、年収が高ければ高いほど容赦なく引かれるものだ。
ちなみに、会社も同額(約100万円)を負担してくれている。
ステップ2:次に引かれる「税金」
社会保険料が引かれたら、いよいよ「税金」の計算に入る。ここで重要なのは、「年収700万円の全てに税金がかかるわけではない」ということだ。
税金がかかる金額(課税所得)を小さくするために、国は「配偶者控除」や「扶養控除」など、様々な「控除」を用意してくれている。控除とは、税金を計算する前の給与から「差し引ける金額」のことだ。
控除の種類とモデル家庭の適用額(超入門編)
このモデル家庭で適用される主な控除は以下の通りだ。
| 項目 | 目的 | 控除される金額(概算) |
| 給与所得控除 | 会社員が仕事をする上でかかる経費代わり | 約180万円 |
| 配偶者控除 | 専業主婦の妻がいる場合の優遇 | 約38万円 |
| 社会保険料控除 | ステップ1で支払った社会保険料の全額 | 約100万円 |
| 基礎控除 | 納税者全員に適用される控除 | 約48万円 |
| 生命保険料控除など | 約10万円 | |
| 合計控除額 | 約376万円 |
つまり、年収700万円からこの約376万円を差し引いた約324万円(課税所得額)に対して、初めて税金(所得税・住民税)がかかることになる。
所得税額の計算(概算)
課税所得が324万円の場合、日本の所得税の税率は10%が適用される。
日本の所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得金額に応じて以下の速算表(令和7年分以降)に基づき税率が決まる。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得324万円は、「195万円から329万9,000円まで」の範囲に含まれるため、税率10%が適用される。
所得税額は、この速算表の税率と控除額を使って以下のように計算する。
所得税額 =課税所得金額×税率 -控除額
3,240,000円×10% – 97,500円 = 226,500円
所得税額は、約226,500円(復興特別所得税を含まない)となる。
【注意点】
- 上記の税率・計算は所得税(国税)のみのものだ。実際には、このほかに住民税(地方税)も課税される。
- 住民税の税率は、一般的に課税所得に対して約10%(均等割を除く)。
- 2037年までは、所得税額に対して復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算される。
所得税と住民税の計算
課税される金額(課税所得)が決まると、それに応じて税率が決まり、所得税と住民税が計算される。
| 項目 | 年間税額(概算) |
| 所得税(国に納める税金) | 約23万円 |
| 住民税(地方自治体に納める税金) | 約30万円 |
| 合計 | 約53万円 |
結論:年収700万円で引かれる総額と手取り
最後に、このモデル家庭で年収700万円からどれだけのお金が引かれているのか、合計額を見てみよう。
| 項目 | 年間費用(概算) | 備考 |
| 社会保険料(ステップ1) | 約100万円 | 厚生年金、健康保険など |
| 所得税・住民税(ステップ2) | 約53万円 | |
| 合計 差し引き額 | 約153万円 | |
| 年間手取り額(現金) | 約547万円 | 700万円 − 153万円 |
年収700万円と言っても、約153万円が税金や社会保険料として引かれているのが現実だ。月々で考えると、約12.7万円が自動的に差し引かれていることになる。
給料明細で歩合給と残業手当の金額の確認しかしないアホ面の同僚には関係ない話かもしれない。そんなアホ面にはこの話は馬耳東風となるだろう。DCには加入せず全額受取りにして無駄遣いをさせておけばいい。
聡明なあなたはこの「引かれているもの」の仕組みを理解することで、「DCに拠出することで、この差し引き額を減らせる(節税できる)」というDCのメリットがいかに大きいか、直感的に理解できるはずだ。