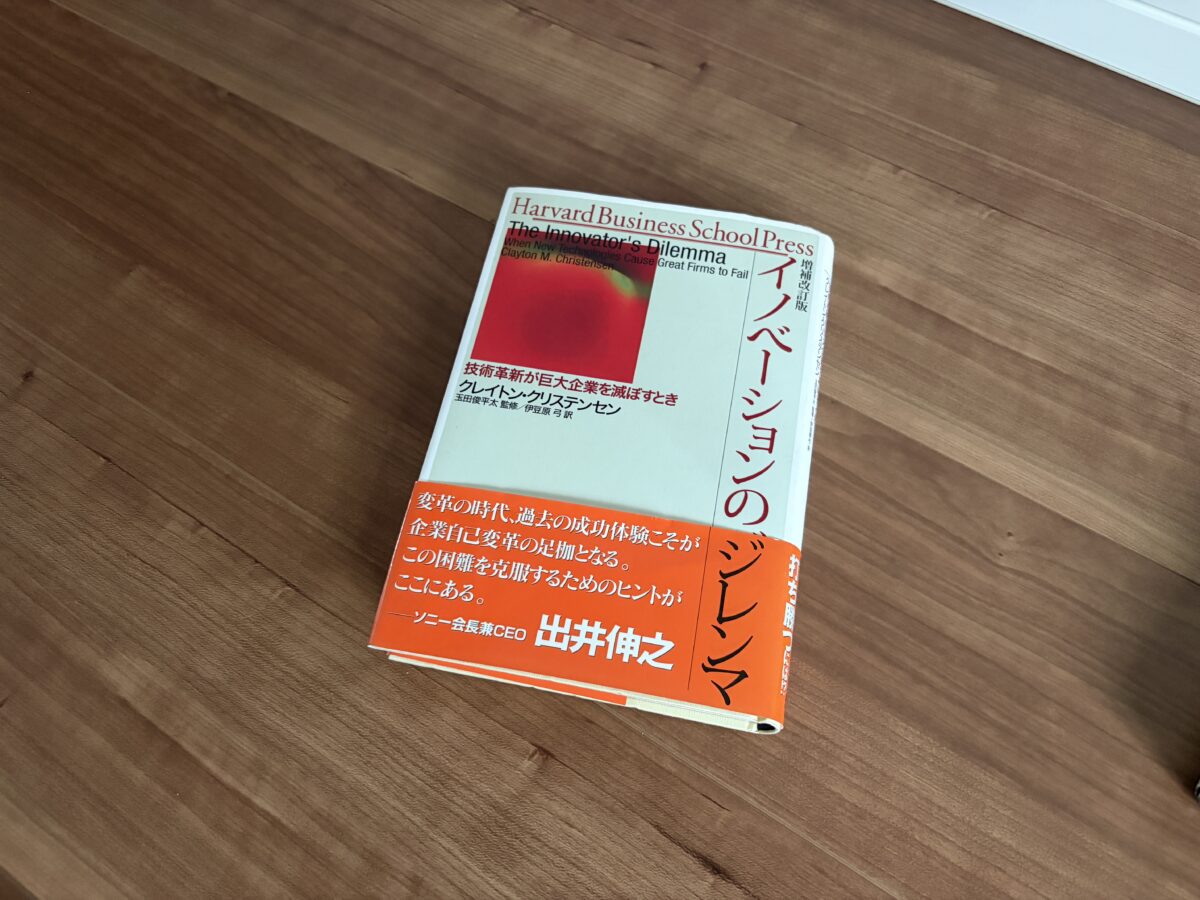「イノベーションのジレンマ」という言葉を聞いたことがあるだろうか。アマゾンで検索してみてほしい。書籍がヒットする。
これは、ハーバード大学のクレイトン・M・クリステンセン教授が提唱した経営理論だ。一言で言ってしまえば、「成功している優良企業が、正しい選択を続けたのに、衰退してしまう」という、ビジネスにおける矛盾を解き明かしたものだ。
「成功しているからこそ対応できるのでは?」と疑問に思う。ここにビジネスのジレンマが隠されている。
1. イノベーションには「2つの顔」がある
「イノベーションのジレンマ」ではイノベーションには2つの種類があると説明されている。
1. 持続的イノベーション
これは、既存の製品やサービスを、より良くしていく種類のイノベーションだ。既存顧客が求めている「より高性能に」「より便利に」という改善であり、企業は当然積極的にこれに取り組む。利益率を高め、成功体験を強化する、いわば「優等生」のイノベーションだ。
2. 破壊的イノベーション
もう一つが「破壊的イノベーション」と呼ばれるものである。これは最初は低品質で安価な製品から始まり、徐々に性能を上げることで、最終的に既存市場を根底から覆してしまうというイノベーションだ。
破壊的イノベーションは、初期段階では既存の優良顧客のニーズを満たさない。そのため、優良企業は初期段階の破壊的イノベーションを「低品質で低収益」と軽視し、持続的イノベーションに集中する。多くの企業が、この破壊的イノベーションの脅威を見過ごしてしまうこと、これこそがジレンマの本質といえる。
2. 没落の具体例:名門企業がが陥った罠
このジレンマの最も分かりやすい例が書籍内で取り上げられている。かつて業界を支配していたIBM、コダック、そしてノキアの物語である。
1. IBMとメインフレームの過信
IBMは現在でも知らない人のいないアメリカのテクノロジー関連の巨大企業だ。1960~70年代、IBMは大型コンピュータ(メインフレーム)市場の絶対的王者だった。メインフレームとは企業の基幹システムに使われる、信頼性・安定性・セキュリティに優れた大型の高性能コンピューターだ。汎用コンピューターやホストコンピューターとも呼ばれ、現代でも金融機関や官公庁など、大量のデータを扱う重要な業務を支えている。
1960~70年代のIBMは大企業や政府機関の顧客が求める、より高速で大規模なデータ処理能力をひたすら追求し続けた。
そこに登場したのが、初期は「おもちゃ」のような存在だったパーソナルコンピュータ(PC)である。初期のPCは性能が低く、既存顧客は見向きもしなかった。だがPCは徐々に性能を上げ、当時メインフレームなどに縁のなかった個人や中小企業という新たな市場を築き、PCはコンピューティングの主流となった。IBMはPC技術を外部のインテルやマイクロソフトに依存した結果、新しい時代の主導権を握ることはできなかった。
2. コダック:自ら開発した技術を恐れた巨人
コダックはアメリカの写真用品メーカーで、かつてはフィルムやカメラの分野で世界を席巻し業界を牽引した。「より鮮明な画質」を求めてフィルムを改良し続けた、持続的イノベーターの代表である。
コダックは1975年にCCDイメージセンサを使用した自己完結型電子カメラを発明し製造した。初期のデジタルカメラは画質が悪く、主流顧客は「こんなのおもちゃだ」と見向きもしませんでした。
コダック自身もその技術を本格的に展開すれば、主力事業であるフィルム販売の収益が激減してしまう。このジレンマに陥り、デジタル技術への投資をためらった結果、ソニーやキヤノンといった後発企業に市場を奪われ、最終的に破産に至った。
3. ノキア:iPhoneを「流行らない」と判断した末路
ノキアは、丈夫でバッテリーが長持ちし、操作しやすい携帯電話(フィーチャーフォン、ガラケー)を追求した、市場の圧倒的王者だった。
そこに登場したのが、アップルのiPhoneだ。初期のタッチパネルは操作しにくく、バッテリーも持たない。しかし、iPhoneは「アプリ」という新たな価値観を創出し、人々の心を掴んでいった。ノキアは自社の成功体験に囚われ、「スマホなんて流行らない」と対応が遅れ、わずか数年で市場の支配的な地位を失った。
3. 日本の事例:ヤマト運輸「宅急便」の破壊力
「イノベーションのジレンマ」の書籍から離れて、日本でのイノベーションのジレンマの事例を考えてみたい。最も分かりやすいのがヤマト運輸が起こした「宅急便」の物語である。
1. 郵便小包の「持続的」な限界
1970年代初頭、日本で小包といえば郵便局の郵便小包が圧倒的な地位を占めていた。国が運営するサービスとして、集荷は原則窓口持込、配達は平日昼間のみという、公平性と効率性を重視した画一的なサービスであった。小包は手紙・ハガキと同じルートで運ばれており、細かな個別対応をする仕組みにはなっていなかった。既存市場の論理で動く、まさに「持続的イノベーション」の権化だ。
2. 宅急便:低収益市場からの破壊
ヤマト運輸は、オイルショックを機に、一般の個人客向けの小口荷物輸送、後の「宅急便」へと舵を切った。これは既存の郵便小包から見れば、低収益でニッチな市場への参入であった。
しかし、ヤマトが提供したのは、郵便小包にはない全く新しい価値だった。
- 利便性の追求: 「電話一本で集荷に伺う」
- きめ細やかさ: 「日曜日も配達する」「留守なら再配達する」
ヤマトは、小型トラック(車)を主体とし、個人宅を巡回する集配方式を採用した。これは「郵便物と一緒」にオートバイや自転車で運ぶ郵便局の仕組みとは全く異なり、小口荷物の集荷・配達に特化したルートと体制だった。
この宅急便は、高性能を追求したものではない。しかし、利便性、きめ細やかさ、そして個人客目線という、従来の小包にはなかった新しい価値基準を持ち込んだ。結果、主婦や個人事業主といった層から爆発的な支持を集め、市場のルールそのものを書き換えてしまったのだ。
当時の郵便事業にとって、宅急便は初期には小さすぎて気にも留めない存在だっただろう。優良企業が、低性能・低収益に見える「破壊的イノベーション」を軽視し、その波に乗り遅れる。これこそが『イノベーションのジレンマ』が示す典型的な構図であるといえる。
4. 破壊者が「ジレンマ」に陥る時:ヤマト対Amazon
ビジネスの世界では、今日のイノベーターが、明日のジレンマの当事者になる、ということが往々にして起こる。宅急便で市場を塗り替えたヤマト運輸もジレンマの当事者になる日がやってきた。
1. ヤマトの「高品質」という成功体験
宅急便を始めたヤマト運輸は、その後も「時間指定」「クール宅急便」など、顧客の利便性を高める持続的イノベーションを積み重ね、日本の小口配送の王者となった。ドライバーのマンパワーを使い、一人ひとりに手厚く丁寧なサービスを提供し続ける。これは、優良企業として当然の、合理的な経営判断であった。
しかし、この「高品質・高サービス」という成功体験が、新しい波への対応を難しくしていく。
2. Amazon「システムとデータ」による破壊
そこに現れたのが、グローバルECの巨人、Amazonだ。
Amazonが持ち込んだ破壊的イノベーションは、ヤマトが大切にした「きめ細やかな対面サービス」とは異なる、「早さ」「安さ」、そして「データによる最適化」という全く新しい価値基準であった。
Amazonは、FBA(フルフィルメント by Amazon)を構築し、「人によるサービス品質」ではなく、「システムとデータによる圧倒的な効率」を追求した。
- ヤマトの価値基準: ドライバーのスキル、再配達の丁寧さ、対面サービス。
- Amazonの破壊的価値: 送料無料(実質無料)、最短翌日配送、そして「置き配」などの非対面サービス。
当初、日本の優良な物流企業から見れば、Amazonが求める「無制限の翌日配送」は、利益率を圧迫する無理な要求に見えた。ヤマト運輸は、既存の高品質を維持しようと合理的な判断をした結果、「低コスト・高効率」という新しい価値基準(破壊的イノベーション)の波に、運送コストという形で対応しきれなくなるという、「イノベーションのジレンマ」そのものの状況に陥ったのだ。
かつて郵便小包を駆逐したヤマト運輸が、今度はより巨大で、システム化された破壊者、Amazonに直面する。この事例は、どんな優良企業でも、新しい価値基準を持つ破壊的イノベーションの前には例外ではないという、クリステンセン教授の理論の恐ろしさと深さを現代に示している。