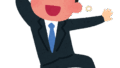2023年10月に酒税の制度の変更があった。
それに伴って、「第三のビール」が値上がりするとの報道が流れ、スーパーや量販店では“駆け込み需要”という名の小さなパニックが起きていた。
その頃ワタシもその現場を目撃してしまった。
とある大型量販店の酒類売り場。そこには信じがたい光景が広がっていた。
カートに10ケースの第三のビールを積み上げているサンダル履きの中年夫婦。
重さに耐えきれずグラつくカートの車輪はギシギシと悲鳴を上げ、床に擦りつつもなんとかレジへと運ばれていく。ふたりは無言。なぜだか少し満足げな表情で、ただ前を見つめていた。
その姿はまさに“酒の亡者”とでも呼ぶべきものだった。
正直、ゾッとした。
飲まなきゃタダなんだが
もちろん、気持ちはわかる。
酒好きにとって「値上がり前に買いだめする」のは、本能的な行動とも言える。
嗜好品とはいえ、毎日飲む人にとっては“生活必需品”のようなものなのかもしれない。
安く買えるなら、買っておきたい。それが消費者心理だろう。
だが、それにしても10ケースは多すぎる。
よほどの酒豪でもなければ、数ヶ月は保つ量だろう。
そして、思ってしまったのだ。
「いや、そもそも飲まなきゃタダなんだが?」
この一言に尽きる。
飲酒は義務ではない。誰かに強制されているわけでもない。
趣味であり、嗜みであり、単なる個人の“選択”にすぎない。
にもかかわらず、その“選択”に対して課税されるのが嫌だからといって、酒を山積みにして買いだめするのは、滑稽としか言いようがない。
なぜそこまでしてまで、第三のビールを確保しなければならないのか。
それほどまでに、酒は人を支配するのか。
「俺の酒税が国を支えている」くらい言ってほしい
もしも彼らが、堂々とこう言っていたら、むしろ清々しかったかもしれない。
「税金を払うために飲んでるんだ。我々の払う酒税が、この国の財政を支えているんだ!」
と。
そうだ。飲むなら飲むで、そのくらいの気概を持っていてほしい。
「うまい!酔いたい!楽しい!でも税金は嫌!」なんて、あまりにみみっちいではないか。
趣味に金がかかるのは当然のことだ。
釣りだって、ゴルフだって、音楽だって、すべてコストがかかる。
その上で「好きだからやっている」という美学がある。
しかし、酒についてはなぜか「できるだけ安く済ませたい」「でも飲みたい」という精神が表に出すぎているように感じる。
だから、10ケースの第三のビールを積んだカートの夫婦を見ると、ただの倉庫作業にしか見えないのだ。そこには趣味性も、気概も、美学もない。
美学がない飲酒行動は、ただの“依存”である
たとえば、両手にガブガブ君(安いペットボトル焼酎)を持ってレジに並ぶおじさんのほうが、まだマシだと思う。
そこには「俺はこの液体で今日を生き抜いて死んでいく」という意思がある。
悲壮感すら帯びていて、逆に美しい。
自分のスタイルを貫くその姿勢には、ある種の信念すら感じる。
だが、第三のビールを10ケース抱えてレジへ向かう夫婦の姿に、そんな気概は感じられなかった。
ただただ「安いうちにできるだけ確保したい」という貧乏倉庫的精神だけがにじみ出ていた。
それがとても寂しかったのだ。
そもそも、その10ケースで何が得られるのか
そもそも、その10ケースを飲み切るのに、どれだけの時間がかかるのだろう。
1日2缶飲んだとして、1ケース=24本だから、10ケースで240本。
つまり、120日=約4ヶ月分の在庫を買いだめしている計算になる。
その間、毎日2本の第三のビールを消費するわけだ。
飲む時間は1時間から2時間程度。
週末はもう少し長くなるかもしれない。
それに加えて、翌日のだるさや頭の重さもあるだろう。
つまり、その10ケースは数十時間〜数百時間分の“酔った時間”を内包していることになる。
もしその時間を、読書や筋トレ、学びや創作に使っていたとしたら、何が変わるのか。
飲んだ後に眠くなってテレビを観て終わる1時間と、フル覚醒で集中した1時間では、得られる密度が桁違いだ。
安いビールを安く確保しても、消費されていくのは金と時間と健康と精神力だ。
そのことを、どうか一度立ち止まって考えてほしい。
“駆け込み酒”の本質は、依存の見えづらい表れである
ここであえて厳しいことを言わせてもらうと、「値上がるから買っておこう」という行動には、依存の兆候が潜んでいると思う。
「値上げされると困る」
「安いうちに買いだめしておかなければならない」
という思考は、裏を返せば「ないと困る」「切れると落ち着かない」という感覚である。
それは嗜好ではなく、依存の入り口だ。
本当に嗜みで飲んでいるのなら、値段が多少上がっても「まぁ仕方ないか」と思える余裕があるはずだ。
でもそれができないというのは、もはや酒のほうが主導権を握っている状態である。
飲むなとは言わない。だが、自分で選べ。
誤解してほしくないのだが、私は禁酒を勧めたいわけではない。
酒を楽しむこと自体を否定しているわけでもない。
だが、自分の行動に対して自覚を持ってほしいのだ。
「飲みたいから飲む」のか、「飲まないと落ち着かないから飲む」のか。
この違いはとても大きい。
もし前者であるなら、その10ケースの買い込みは、美学のある“戦略的消費”かもしれない。
だが後者であるならば、それはもう依存に支配されている証拠だ。
最後に
サンダル履きの中年夫婦が、重たいビールケースを積み上げて、カートをギシギシ言わせながらレジへ向かうあの光景。
それは単なる「値上がり前のまとめ買い」ではなく、現代人が抱える“逃れがたい依存”の縮図に見えた。
酒を飲むこと自体は自由だ。
だが、その選択に主体性はあるか?
その酒は、あなたにとって喜びなのか? それとも逃げ場なのか?
カートを押す手をとめて考える余裕はあの夫婦にはなさそうだ。あなたはどうだろう。